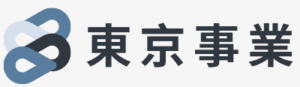KDDIエボルバとりらいあコミュニケーションズ、統合会社アルティウスリンクを発足 | 2023年 | KDDI株式会社
~デジタルBPOで高みを目指し信頼のパートナーへ~
株式会社KDDIエボルバ
りらいあコミュニケーションズ株式会社
KDDI株式会社
三井物産株式会社
2023年7月20日
KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:髙橋 誠、以下 KDDI)の完全子会社である株式会社KDDIエボルバ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:若槻 肇、以下 KDDIエボルバ)と、三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:堀 健一、以下 三井物産)の持分法適用会社であるりらいあコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:網野 孝、以下 りらいあ)は、対等な精神に基づく経営統合(以下 本経営統合)に関連し、アルティウスリンク株式会社(以下 アルティウスリンク)を2023年9月1日に発足します(注1)。アルティウスリンクはコンタクトセンターやバックオフィスを含むBPO事業を国内・海外で展開します。両社の顧客基盤を生かし、生成系AI(人工知能)の活用などデジタル化によるサービスの高度化を進め、デジタルBPO(注2)のリーディングカンパニーを目指します。
■背景
労働人口の減少に伴う人手不足や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う企業のデジタル化の加速により社会や企業の課題やニーズが変化しています。コンタクトセンター業界においても、従来業務の人主導からAI主導への代替、消費者接点のデジタル化に伴うコール(音声)からテキスト・Webへのシフトなど、ビジネス環境は転換期を迎えています。一方、企業において自社のみですべてのデジタル化を進めるには課題のある状況です。アルティウスリンクはコンタクトセンターを含むデジタルBPOを展開することで、お客さま企業の成長に貢献します。
■統合会社について
1. 目指す姿
デジタルBPOで高みを目指し信頼のパートナーへ
2. 事業内容
3. 4社のシナジー
アルティウスリンクの事業規模は売上高2,400億円となり、お取引先1,300社以上、従業員約58,000名、拠点数約100拠点となり、国内コンタクトセンターでは売上No.1(注3)の規模となります。アルティウスリンクは以下の各社の強みを組み合わせ、シナジーを最大化していきます。
KDDIエボルバ
コンタクトセンター設計・運営、通信・インフラなど広範な取引先、ITソリューション、エンジニア派遣
りらいあ
コンタクトセンター設計・運営、自治体・インフラ・金融など広範な取引先、海外事業(フィリピン、ベトナム、米国など)
KDDI
ICT領域とデータ領域の知見、AI Chatとメタバース活用
三井物産
ITサービス子会社によるデジタル知見、海外先端技術・サービス発掘とビジネス開発、国内外グループ会社のネットワーク
4. 新社名について
社名をアルティウスリンクに決定するにあたり、ワンチームとしてさらなるコミュニケーションの高みへと進化していこうという強い意志を社名に込めました。ラテン語で「より高く」を意味するALTIUS(アルティウス)と、両社がともに大切にしてきた「つながり」をLINK(リンク)で維持するという意味を込めた「アルティウスリンク」に決定しました。また統合会社のロゴはALTIUS LINKの「AとL」を組み合わせており、高みを目指す姿勢を先進的な突き抜ける直線で表し、人や社会と共に有機的な成長をしていこうという思いを曲線で示しています。また、シンボルマークは「QとA」の掛け合わせでもあり、これは社会やお客さまの問いに、答えとなるソリューションを提供するという私たちの姿勢を示しています。
統合会社の特設ページはこちらをご参照ください。
■アルティウスリンク株式会社(統合会社)の概要(予定)
名称
アルティウスリンク株式会社
登記上本店
東京都新宿区西新宿 二丁目3番2号
代表者の役職・氏名
代表取締役社長 網野 孝、代表取締役副社長 若槻 肇
事業内容
...
ひとことで株価を動かすウォーレン・バフェットが次に狙う日本株 – 経済・ビジネス – ニュース|週プレNEWS
先日来日したウォーレン・バフェット氏。ジョージ・ソロス、ジム・ロジャーズと共に世界三大投資家に数えられる。1930年生まれの御年92歳。ちなみに、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツとは仲良しである世界三大投資家のひとりが、まさかの来日。おまけに「日本株への追加投資をするかも」なんて言うもんだから、相場は大騒ぎ!! 投資した企業がその後軒並み高騰するバフェット氏が、次に狙う企業を識者に聞いた。* * *■バフェットは何しに日本へ?〝投資の神様〟とうたわれるウォーレン・バフェット氏(92歳)が、4月上旬に来日した。投資をしない人にはなじみの薄い名前かもしれないが、世界的に影響力を持つアメリカ人投資家で、約14兆円の資産を持つ世界5位の大富豪でもある。バフェット氏は常々米国の強さを語り、投資先も米国企業がほとんど。そんな彼が、わざわざなぜ日本に?その理由は、彼が日本への投資を拡大しようとしているからだ。さかのぼること3年前、バフェット氏は自身がCEOを務める投資会社バークシャー・ハサウェイ(以下、バークシャー)を通して、日本の五大商社(三菱商事・三井物産・住友商事・伊藤忠商事・丸紅)の株式を取得したことを明かした。以来、各社の株価は軒並み上昇し、丸紅に至っては3倍以上に! バフェットはおそらく、日本への投資拡大というアイデアに自信を深めたことだろう。総合商社は海外との資源取引に強みを持っている。コロナ禍とウクライナ戦争が引き起こしたエネルギー危機により、日本の大手商社はここ1年で莫大(ばくだい)な利益を上げたわけだが、バフェット氏はまるでそのことを1年前に読み切っていたかのようだ。来日時には「日本株へのさらなる追加投資を検討している」との発言も飛び出したが、彼は果たして今後、どんな会社に手を伸ばすのか?核心に迫る前に、バフェット氏の足跡を簡単に振り返ろう。三井不動産の東京ミッドタウン八重洲。都心に優良な物件を保有する同社はバフェット氏好みの銘柄といえる■シンプルすぎるバフェットの投資法バフェット氏はいかにして大富豪となったのか。その答えは驚くほど単純で、投資の成功をひたすらに積み重ねたのだ。物語のスタートは1965年。34歳のバフェット氏は、当時繊維会社だったバークシャーを買収すると、事業再建に着手する。CEOに就任してからは事業を転換し、保険会社や菓子メーカー、電力会社、鉄道会社などさまざまな企業の買収と、優良企業への株式投資を進めたのだ。その結果、58年間でバークシャーの株価はなんと約3万8000倍に成長。当時バークシャー株を1万円分買っていたら、今頃資産額が4億円に迫る大金持ちになっていたわけだ。では、バフェット氏はなぜ50年以上勝ち続けることができたのか? その秘訣(ひけつ)は「よい株を安く買い、長く持つこと」だという。この理屈で彼はコカ・コーラの株式を34年、アメリカン・エキスプレス(アメックス)の株式を29年にわたって保有し続け、巨額の配当を得ている。また、自分に理解できないビジネスには見向きもせず、「10年間持ち続けられない銘柄は10分間ですら持とうと考えてはいけない」と彼は言う。だから、バークシャーはコロナ期間中に株価が暴騰した後、たちまち暴落してしまったハイテク銘柄には見向きもしなかったし、AI株についても「私はわからない」とにべもない。拍子抜けするほど単純なルールを守り、結果を出し続けるからこそ、世界中の投資家から尊敬を集めているのだ。ちなみにバフェット氏は贅沢(ぜいたく)を好まず、毎朝マクドナルドを食べ、一日5缶コーラを飲むという(それで92歳までバリバリ現役なのもスゴい)。収入は役員報酬の10万ドルのみで、58年に米国の地方都市に購入した家に今でも住み続けている。彼の投資哲学は人生哲学にも通じており、それもまた魅力のひとつだろう。■バフェットが次に手を伸ばす業種は?ここからは、バフェット氏の投資手法を詳しく見ていく。株式評論家の坂本慎太郎氏はこう語る。「彼がやっているのは、企業の将来像を見定めて、それに対して現在の株価が安ければ買うという手法。よく『バリュー投資』といわれますが、全然違うと思います。バリュー投資とは、企業が持っている資産や、毎年上げる利益と株価の比率を計算し、割安だったら投資する手法です。これに対して、バフェットが重視しているのは、その企業がこれから先、長きにわたって稼ぐ力。企業の現在を見るバリュー投資と、未来を見据えた上で、それをできるだけ安く買おうという彼の手法は、『安く買う』という点以外はむしろ正反対だといえます」しかし、それならバフェット氏はなぜ日本株に将来性を見いだしているのか? 経済アナリストの馬渕磨理子氏が解説する。「商社株はその典型例ですが、成長力があるのに気づかれず、株価が安く放置されている日本企業はいくつもあります。そうした優良企業を、ほかの人々が魅力に気づいていないタイミングで買うのが彼のスタイル。商社への追加投資も検討しつつ、それ以外にも伸びしろのある銘柄があると思ったからこそ今回来日したのでしょう」(馬渕氏)では、バフェット氏が次に狙う業種、企業はなんだろうか? 「商社は引き続き有望」と語るのは坂本氏。「商社というビジネス形態は日本特有で、海外の投資家にはなじみがありません。日本国内でも昔からある業態ということで、高収益、高配当なのに人気がありませんでした。商社は事業があまりにも多角化しているために、投資家は何を見て判断すればよいのかがわかりにくいのです。その結果、手がける事業の中でも一番株価が割安な業種である『資源セクター』(エネルギーや鉄鉱石などの関連企業)と同程度の水準で放置されていました。要は儲かっているのに、その収益性は長続きしないだろうとナメられていたわけです。バフェットはそこを見抜き、自分の投資によって商社の収益力が適切に評価され、株価が上がると踏んだはず。今後もその流れは続くでしょう」馬渕氏からは、バフェット氏がこれまで投資してきた企業のラインナップが参考になる、とのアドバイスをもらった。「バークシャーの資金量はなにしろ莫大です。自分の売買で株価が大きく振れてしまうような中小企業には投資できないので、誰でも名前を知っているような大企業を選ぶでしょう。バークシャーが米国で大きく投資しており、かつ日本国内に優良企業がある業種といえば、食品・銀行が代表的。ほかにも割安さや日本独自の強みが際立つ業種に注目しています」ここ1年ほど日本株は横ばいで、煮え切らない展開が続いているが、〝投資の神様〟の動きが起爆剤となってもおかしくない。
博報堂、雑誌からジャニー喜多川氏巡る記述削除 広報が判断…「ビジネスパートナーへの配慮のため」: J-CAST ニュース【全文表示】
大手広告代理店「博報堂」が発行する雑誌で、ジャニーズ事務所の創業者・ジャニー喜多川氏の問題を取り上げたものの、同社広報室長の判断で掲載が見送られていたことが分かった。 広報室は取材に「当社のビジネス上配慮が必要とした原稿に関しては、掲載の可否含め編集長と相談の上、判断をしています」と答える。
広告ツイッターより
広告誌面より
...
「DXダイレクトビジネスセンター」を新設 -企業と消費者をダイレクトに繋ぐ、デジタルサービスの事業戦略策定・開発・グロース組織- | 株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、企業と消費者をダイレクトに繋ぎ、デジタルサービスの事業戦略策定・開発・グロースを支援する組織として「DXダイレクトビジネスセンター」を2023年2月に新設いたしました。
...
【セキュリティ ニュース】スモールビジネス向けCisco製ルータに深刻な脆弱性 – 遠隔よりコードを実行されるおそれ(1ページ目 / 全2ページ):Security NEXT
Cisco Systems製ルータ「Cisco Small Business RVシリーズ」の一部製品に深刻な脆弱性が明らかとなった。アップデートが提供されている。
「同RV345シリーズ」「同RV340シリーズ」「同RV260シリーズ」「同RV160シリーズ」の一部ファームウェアに複数の脆弱性が明らかとなったもの。
いずれも「CVE-2022-20827」「CVE-2022-20841」が存在し、くわえて「同RV340シリーズ」「同RV260シリーズ」では「CVE-2022-20842」の影響を受ける。現地時間8月3日の時点で脆弱性の悪用や公開は確認されていない。
今回明らかとなった脆弱性においてもっとも深刻とされるのは、ウェブ管理インタフェースに明らかとなった「CVE-2022-20842」。入力内容の検証に不備があり、細工したHTTPリクエストによって認証なしにリモートよりroot権限でコードを実行したり、サービス拒否の状態を引き起こすことが可能だという。
共通脆弱性評価システム「CVSSv3.1」のベーススコアは「9.8」で、重要度は4段階中もっとも高い「クリティカル(Critical)」とレーティングされている。
(Security NEXT - 2022/08/04 )
ツイート
関連リンク
Cisco Systems:Cisco Small Business RV Series Routers Vulnerabilities
Cisco Systems
PR
関連記事「Cloudflare Zero Trust」にセキュリティ機能バイパスのおそれ機密情報管理のHashiCorp製「Vault」に脆弱性 - データ消失のおそれGoogle、「Chrome 104」をリリース - セキュリティに関する27件の修正を実施VMwareのID管理製品に再び深刻な脆弱性 - 早急に更新の実施を「GnuTLS」に脆弱性 - アップデートがリリースニンテンドーのWi-Fiアダプタに2件の脆弱性 - 利用中止を「Samba」に複数の脆弱性 - ドメインを乗っ取られるおそれも複数のAtlassian製品に深刻な脆弱性 - アップデートがリリース「一太郎Pro」「ATOK」など法人向けジャストシステム製品の同梱プログラムに脆弱性動画配信サービス「Hulu」のアプリに脆弱性
英米の情報機関トップ、中国の「途方もない」脅威をそろって警告 – BBCニュース
7時間前ゴードン・コレラ、安全保障担当編集委員、BBCニュース画像提供, UK pool via ITN画像説明, 英MI5のマカラム長官(左)と米FBIのレイ長官が、ロンドンの会合にそろって出席したイギリス、アメリカ両国の情報機関トップが6日、そろって会合に参加し、中国の脅威について警告した。両者が公の場で一緒に姿を見せるのは異例。会合で米連邦捜査局(FBI)のクリストファー・レイ長官は、中国について、「アメリカの経済および国家安全保障に対する最大の長期的な脅威」だと主張。最近の選挙を含めた米政治に、中国が干渉していたと述べた。英情報局保安部(MI5)のケン・マカラム長官は、過去3年間で中国の動きに対する業務を2倍以上増やしており、さらに倍増させる予定だとした。また、中国共産党の活動に関連するMI5の調査は、2018年と比較して7倍になっていると付け加えた。FBIのレイ氏は、中国が台湾を力によって手に入れた場合、「世界がこれまで目にしたことのないほど恐ろしい、ビジネス面での混乱が生じる」だろうと警告した。両長官が公の会合にともに姿を見せたのは初めて。会合は、英ロンドンのテムズ・ハウスにあるMI5本部で開かれた。中国共産党の脅威について、マカラム氏は「状況を一変させている」と指摘。レイ氏は「途方もない規模」で、「息をのむほどだ」とした。この日の聴衆は、企業トップや大学幹部など。レイ氏は、中国政府がさまざまなツールを使って「あなた方の技術を盗もうとしている」とし、警戒を呼びかけた。レイ氏はまた、中国について、「多くの洗練されたビジネスマンが認識している以上に、西側のビジネスにとって深刻な脅威」になっていると説明。アメリカの農村部で、中国企業とつながりのある人たちが遺伝子組み換え種子を掘り出していた事例を挙げた。掘り出された種子については、独自で開発しようとすれば、何十億ドルもの費用と10年近い年月がかかっただろうと述べた。レイ氏はさらに、中国が「大規模な不正と窃盗」を目的に、サイバースパイ活動を展開していると主張。ハッキングの規模は、他のすべての主要国によるハッキングを合わせたよりも大きいと述べた。一方、マカラム氏は、サイバー脅威に関する情報は37カ国と共有していると説明。5月には航空宇宙に対する高度な脅威を解消したとした。画像提供, Getty Images画像説明, 中国はロシアのウクライナ侵攻から教訓を得ているとの見方で、両長官は一致したマカラム氏はまた、中国に関するさまざまな事例を紹介。魅力的な雇用の機会をオンラインで提供された、英航空専門家のケースについても話した。この専門家は2度にわたって中国を訪れており、飲食を振る舞われた後、中国情報機関の見せかけだった企業から、軍用機の技術情報の提供を求められていたという。「そのとき私たちが介入した」とマカラム氏は話した。さらに、あるエンジニアリング会社は、中国企業から接触され、技術を持ち逃げされた後に取引が中止され、2020年に経営破綻に追い込まれたと述べた。マカラム氏は、クリスティン・リーという名前の女性の活動に関して、議会が1月に出した警告についても指摘した。この種の活動は、親中国共産党の主張を増幅させ、同党の権威を疑問視する声を封じるのが目的であり、「問題視される必要がある」とマカラム氏は話した。「台湾への関心は薄れてない」FBIのレイ氏は、米ニューヨークでこの春にあった下院選挙に、中国政府が直接的に介入してきたと述べた。天安門事件の際に抗議に加わっていた、中国に批判的な候補者を当選させないのが狙いだったとした。レイ氏によると、中国政府は私立探偵を雇い、名誉を汚すような情報を探らせたという。何も見つからないと、セックスワーカーを利用して物議を醸そうとしたり、交通事故を演出することを提案したりしたという。レイ氏は中国について、ウクライナの紛争から「あらゆる種類の教訓」を得ようとしていると述べた。ロシアが科されたような制裁から将来的に身を守る方法も、その1つだという。もし中国が台湾を侵略すれば、経済的混乱は今回よりはるかに大きく、西側の対中投資は「人質」となり、サプライチェーンは破壊されるだろうと、レイ氏は述べた。レイ氏は会合での講演後、記者団に、「中国の台湾への関心が少しでも薄れたと考える理由はない」と話した。MI5のマカラム氏は、新しい法律が脅威への対処に役立つだろうが、イギリスは「より困難な標的」になる必要があるとした。そのためには、社会のあらゆる部分がリスクをもっと認識することが求められるとした。また、査証(ビザ)制度の改革により、中国軍に関連する50人以上の学生をイギリスから退去させたと述べた。レイ氏は、「中国はあまりにも長い間、どの国の優先事項でも2番目であることに乗じてきた」とし、こう付け加えた。「中国はもはや、気づかれないように行動しているわけではない」。
伊藤忠商事/リニューアブルディーゼルタンクローリー使用開始 ─ 物流ニュースのLNEWS
伊藤忠商事、伊藤忠エネクス、INPEX、INPEXロジスティクスの4社は、再生可能資源由来燃料であるリニューアブルディーゼル(Renewable Diesel、以下「RD」)の日本初となるタンクローリー車での使用に係る協業に着手したと発表した。
<リニューアブルディーゼルを使用するタンクローリー>
これにより、INPEXロジスティクスは、伊藤忠商事が世界最大のリニューアブル燃料メーカーであるNeste OYJから調達し、伊藤忠エネクスが供給するRDを、北陸・甲信越地方で国産原油及び石油製品の輸送を担う18台のタンクローリー車の燃料として使用する。同地域でのRDの利用並びにタンクローリー車でのRD使用は日本初となる。
この取組に先立ち、伊藤忠商事はNesteとRDの日本国内向け輸入契約を締結、伊藤忠エネクスは国内のRD輸送及び給油に係る一連のサプライチェーンの構築を行った。この取組は、これらにINPEXグループが既に確立している北陸・甲信越地方を中心とした販売網を組み合わせることにより実現したもの。
今後4社は、INPEXロジスティクスが保有するタンクローリー車への継続的なRD供給及びその使用により、陸上輸送分野での脱炭素化を牽引していく。また取組を通じて、INPEXグループが有する北陸・甲信越地方を中心とするネットワークを活かしたRDのビジネス展開に向けた協働を進め、共にサーキュラーエコノミー及び脱炭素社会の実現に寄与することを目指していくとしている。
なお、NesteのRDは食品競合の無い廃食油や動物油等を原料として製造され、ライフサイクルアセスメントベースでのGHG排出量で石油由来軽油比約90%の削減を実現。RDは主に輸送用トラック・バス等で使用され、所謂「ドロップイン」燃料として、既存の車両/給油関連施設をそのままに利用開始することが可能で、既に欧米を中心に広く流通実績がある。脱炭素施策に係る導入コストを最小限に抑え、GHG排出量削減にも大きく貢献できる次世代リニューアブル燃料として、今後の陸上輸送分野での更なる利用拡大が期待される。
...