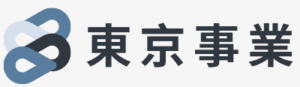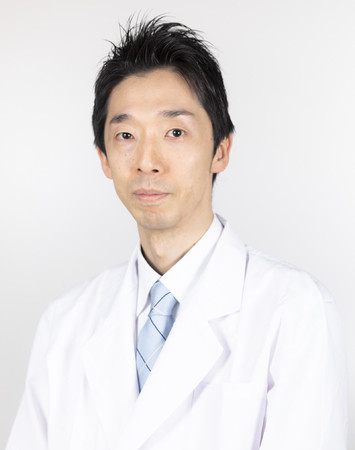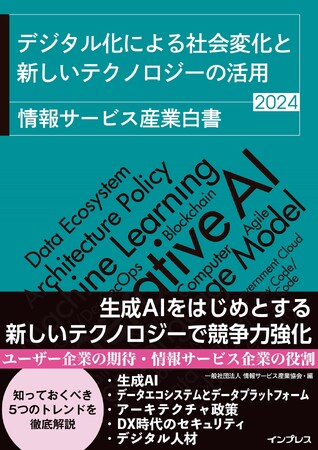2027年までの地域予測によるGPONテクノロジー市場の新興テクノロジー – securetpnews
Global GPON Technology Market Research report represents an extended study of global GPON Technology industry by delivering an evaluation of the present future trends, competitive forces, client expectations, technological advancements, and effective capital in...
米テクノロジー大手に反トラスト法案、下院超党派議員が公表 – Bloomberg
米下院の超党派議員団は11日、アマゾン・ドット・コムやアップルなど米テクノロジー大手に対する包括的な反トラスト(独占禁止)法案を公表した。 関連法案は計5本。プラットフォーム運営企業が主要事業の売却や撤退を迫られ、ビジネス運営に著しい制約が加わる可能性がある。
...
【受講料無料】地域に新風を巻き起こす。2日間短期集中プログラミングコース|プログラミング、やってみよう。『G’s CAMP SAIKAI』|G’s ACADEMY|デジタルハリウッド株式会社のプレスリリース
■2.5日でセカイが一気に変わる。現役エンジニアがプログラミングの基礎を徹底指導テクノロジーのチカラで「セカイを変えたいという」強いモチベーションがさえあればプログラミング未経験でも参加OK。
現役エンジニアの講師と、約20時間の講義+オンライン動画でプログラミングの基礎を徹底指導します。※エントリー後、書類選抜あり
■地方をテクノロジーで盛り上げたい、エンジニアコミュニティを根付かせたいG’s CAMP...
デジタル時代の伝統芸能–テクノロジーとの融合で次世代に魅力を継承 – CNET Japan
伝統芸能である歌舞伎、能楽、文楽などは、無形の技術であり、世代から世代へと伝えられてきた。伝統芸能は、日本の古い芸術や技術を総称を指す。演劇、音楽、舞踊、演芸などが含まれており、多くは明治時代以前に栄えた。これらの芸能は無形の技であり、長い年月をかけて師匠から弟子へ、親から子へと受け継がれてきた。特に能楽、文楽、歌舞伎、雅楽、組踊は、ユネスコの無形文化遺産に登録され、世界的な評価を受けている。しかし現在、高齢化が進むなかで、後継者不足による伝統芸能の途絶が深刻な問題となっている。
そこで、テクノロジーを活用して伝統芸能の継承を支援するためにさまざまな取り組みも行われている。長く受け継がれてきた文化は世代を超えて人々を結びつけ、社会的な役割を果たしている。そのため、伝統芸能の保存方法は重要な文明の発展においても重要と考えている。
近年のテクノロジーの進歩により、3次元の動きをデジタルデータとして記録するモーションキャプチャ技術が、より手軽に利用できるようになってきた。VRゴーグルであるVRヘッドマウントディスプレイ(VR HMD)と組み合わせたり、あるいはスマートフォンと小型センサーを活用したり、スマートフォンだけでも全身トラッキングができるようなアプリもあり、個人でも手軽にモーションキャプチャを行うことが可能で、仮想空間のキャラクターを動かすことも容易になった。
そこで本記事では、VR技術が伝統芸能に与える可能性について考えていく。
VRデバイスを使わずに、バーチャル空間を表現
VR能公演「VR能攻殻機動隊」は、士郎正宗さんのSF漫画「攻殻機動隊」を、日本の誇る古典芸能である「能」で表現した取り組み。このプロジェクトでは、最新技術の「空中結像技術(AIRR)」を駆使して、VRヘッドセットなしでも仮想現実空間を舞台上で表現する新しい試みが行われた。
「VR能攻殻機動隊」キービジュアル
(C)士郎正宗・講談社/TBS・EVISION
演出は、「ペルソナ」シリーズや「攻殻機動隊 ARISE」、AKB版「仁義なき戦い」など、実現が難しいと思われる数々の舞台作品を成功に導いてきた映画監督、奥秀太郎氏が担当。脚本は、アニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」や「BLOOD」シリーズで知られる脚本家の藤咲淳一氏。映像技術は、「攻殻機動隊 ARISE」舞台版や3D能シリーズなどを手がけ、日本初の舞台での3D映像を開発してきた福地健太郎氏(明治大学教授)。VR技術は国内のVR研究の第一人者として知られる稲見昌彦氏(東京大学教授)など、各分野の最先端を行く方々が関わっていた。
また、出演者として坂口貴信氏、川口晃平氏、谷本健吾氏など、実力と知名度ともに能のシーンをリードする観世流能楽師が名を連ねた。これらの先駆的な技術と日本の伝統芸能が高度な次元で結びつき、攻殻機動隊の世界を再現する未来の舞台芸術が創造された。
能は厳格な型に従っており、歴史のなかで長い時間をかけて形成され、余計なものを排除し、そのスタイルが確立された。そのシンプルで優雅な動きは、日本の伝統芸能として世界的に認められている。
攻殻機動隊は現実と電脳空間の出来事が曖昧で、どちらが現実か区別が難しい作品とされており、それをテーマにVRで能を再現することにより、現実と仮想が一体となった世界観を生み出すことができる。空中結像技術によってホログラムのように演者が突如出現したり消失したりするシーンはSFの世界がまさに再現されているかのようだ。アニメとは異なる味わいがあるが、全く新しい、想像力に富んだ能の世界が生み出されている。能独自の幻想的な要素が舞台上で見事に調和し、光学迷彩がリアルな舞台で、肉眼で見ることができるのだ。
https://www.youtube.com/watch?v=h2FVFQJYRh0
このように、700年にわたる能の歴史を続けていくためには、新しい作品を創造することが重要である。映像と舞いが融合し、新しい化学反応から新しい表現方法やこれまでにない文化の紡ぎ方の可能性を示せているのではないだろうか。
VTuberは現代版文楽か?
VRChatをはじめとするメタバースでは、ユーザーは自分の身体の代わりとなる「アバター」を使ってコミュニケーションを取る。
【関連記事:「VRChat」は日本ユーザーにも優しい世界がある—これから始める方にお勧めのイベント】
【関連記事:アバターが作り出すメタバースの世界—アバター主義で多様化する生き方】
アバターを使って動画配信をするVTuberの存在も日常的になった。一般的にVTuberは、いわゆる“中の人”がモーションキャプチャで取得した自身の動きのデータをアバターに反映させ、声を吹きこむことで配信をしている。「VTuberはそれ自体で存在している」と筆者も本当は思いたいところだが、仕組みとしてアバターの裏には実在の人が存在しているため、「現代版文楽」とも言うこともできるだろう。
VTuberの動きは、日本の人形芝居を思わせる。日本の芸能の中で最も古い形態のひとつは、傀儡(くぐつ)と呼ばれる人形を使った芝居である。古くから、日本では人形に何かを演じさせたり表現させたりすることが好まれてきた。その中でも代表的なものが人形浄瑠璃だ。人形を使って感情を表現するのは、人間が演じるよりも高度なテクニックが必要である。
VTuberも同様に、アバターを動かしているのは実際の人物である。ここには伝統的な人形浄瑠璃と通じる要素があるとも言える。人形が悲しむ仕草の方が、人間が悲しむ演技をするよりも心に訴えかけることがあるように、VTuberもその裏にある人がアバターを通じて感情を表現することで、視聴者の心に深く響くのかもしれない。
...
Relicが提供する国内シェアNo.1のSaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」が『Ruby biz Grand prix 2021』でDX賞を受賞
[Relic]
日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する事業共創カンパニーである株式会社Relic(代表取締役CEO 北嶋 貴朗、東京都渋谷区、以下、Relic)が提供する、国内シェアNo.1のSaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」が、Ruby biz グランプリ実行委員会(事務局:島根県 商工労働部 産業振興課 情報産業振興室)が主催するITビジネスコンテスト『Ruby biz Grand prix 2021』にて国内25事例の中からDX賞を受賞しました。■DX賞の受賞について 弊社RelicのThrottleが受賞したDX賞は、ビジネス現場の課題を解決するプラットフォームを展開し、イノベーションの創出や業務変革の実現に挑戦する企業に贈られる賞です。・受賞コメント - グロースマネジメント事業本部 プロダクトマネージャー 田中 翔太良 はじめまして、株式会社Relicの田中と申します。この度はこのような賞をいただきまして誠にありがとうございます。弊社は、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」と称して、新規事業開発における総合的なソリューションを提供しており、これまでに3,000社・15,000以上の事業プランやアイデアに関与するなど国内トップクラスの新規事業支援実績があります。 その中でも、「Throttle」は、新規事業創出プログラムや社内ベンチャー制度、オープンイノベーションやアクセラレーションプログラム等を含む、すべての新規事業開発を総合支援し、イノベーション創出を加速するための活動に最適化されたSaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォームとなります。 今後の日本企業においてイノベーションマネジメントの概念や手法が普及し、新規事業創出への取り組みを試みる企業が増加していくと想定される中で、今回賞をいただきました「Throttle」が、挑戦する企業や組織の支援に少しでも寄与できれば幸いです。■Ruby biz Grand prixについて Ruby biz Grand prixは、プログラム言語「Ruby」を活用して、ビジネスの領域で新たな価値を創造し、今後の発展が期待できるサービスや商品を表彰するグランプリです。企業はRubyを使った開発により、時代の変化に柔軟に対応し、企業・社会が抱える課題に対してスピーディーにアプローチすることができます。本グランプリを通して、Rubyがもたらす革新性を国内外に広く発信し、IT産業全体の振興に貢献いたします。Ruby biz Grand prix専用サイト:https://rubybiz.jp/■イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」とは Throttleは新規事業創出プログラムや社内ベンチャー制度、オープンイノベーションやアクセラレーションプログラム等を含む、すべての新規事業開発やイノベーション創出のための活動に最適化されたSaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォームです。今後の日本企業においてイノベーションマネジメントの概念や手法が普及し、新規事業創出の取り組みを試みる企業が増加していくと想定される中、新規事業開発やオープンイノベーションにおけるアイデア創出から事業化に至るまでの一連のプロセスを一元的に管理・運用できる仕組みとテクノロジーを提供することで、挑戦する企業や組織の支援を行うことを目的に2019年8月より提供を開始しました。 すべての挑戦者を支援して「インキュベーションの民主化」を実現するべく、Relicがこれまで大企業~スタートアップまで3,000社以上の企業と15,000以上の新規事業を支援して蓄積したナレッジやノウハウをオンラインで提供し、プロフェッショナルネットワークやデータベースと連携することで事業構想や新規事業立案、仮説検証や事業化までのトータルサポートをSaaSで実現するものです。■イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」の詳細はこちらサービスサイトURL:https://relic.co.jp/services/throttle/サービス紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=e5THnInjmTo活用事例のダウンロード:https://relic.co.jp/services/throttle/wpdl/■株式会社Relicについて Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」です。2,000社以上が利用する国内シェアNo.1のSaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」や、国内シェアNo.1のSaaS型クラウドファンディング構築サービス「ENjiNE」、顧客のロイヤリティを向上し、事業のグロースをマネジメントする次世代型マーケティングオートメーション/CRM「Booster」等の「インキュベーションテック事業」に加え、新規事業開発における事業プロデュースやコンサルティング、オープンイノベーション支援、新規事業創出プログラムや社内ベンチャー制度の企画・設計・運営や、事業開発に特化した共創型エンジニアリングサービス「Digital Innovation Studio」、ベンチャー・スタートアップ投資など総合的なソリューションを提供しており、大企業~中小・ベンチャー企業まで業界トップクラスである3,000社以上の支援実績があります。・コーポレートサイト:https://relic.co.jp/・事業内容:https://relic.co.jp/services/【本リリースに関するお問い合わせ先】株式会社Relic 担当:田中・佐々木 [email protected] 03-6455-0735 03-6869-9452企業プレスリリース詳細へ
(2021/12/15-20:47)
株式会社ハシタスはFC E’XITO YOKOHAMAとプロダクト開発における実証実験パートナー契約を締結しました。|株式会社ハシタスのプレスリリース
■新しいスポーツトレーニングアプリを目指して
ハシタスが開発しているメタ練はAIを活用した新しいスポーツトレーニングアプリを目指しており、実際のスポーツ指導の現場、トレーニングを受ける選手にとってスポーツ能力の向上に寄与するのかという観点を実験・評価するためにFC E'XITOと実証実験パートナー契約を締結しました。学術的パートナーを結んでいる夏原准教授とともに、「メタ練」を使ってスポーツ能力を向上させる共同研究を行っていきます。
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=104206&release_id=5&owner=1■FC...
Japan Innovation Review powered by JBpress
大日本印刷 常務執行役員の金沢貴人氏(撮影:酒井俊春)
大日本印刷(DNP) が、デジタル技術を活用した新規事業開発に取り組んでいる。背景にあるのはデジタル化による紙の印刷 減少への危機感だ。他社とも連携し、XR(クロスリアリティー)、量子コンピューターなど先端技術分野での新規事業創出を目指す。どのような体制で、どんな取り組みを行っているのか。新規事業開発を担うABセンター長の金沢貴人氏に話を聞いた。
生き残るために「次は何をやるんだ」という組織風土が根付く
――金沢さんの肩書きには、新規事業創出を担うABセンター長の他にもCIOとあります。 “攻めのDX”と“守りのDX”のトップを兼務されていますが、どのような役割を担っているのですか。
金沢 貴人/大日本印刷 常務執行役員 ABセンター長 教育ビジネス本部担当 コンテンツ・XRコミュニケーション本部担当 情報システム本部担当 情報セキュリティ委員長 技術・研究開発本部ICT統括室担当1984年、大日本印刷入社。研究開発部門に長らく携わり、印刷原版を作成するCADシステムの設計開発などに従事した後、製造の技術部門、企画部門を経験。現在はABセンターなどの新規事業創出部門と情報システム本部、情報セキュリティ本部(DNPグループのCIO)、技術・研究開発本部ICT統括室を担当。BIPROGY取締役(非常勤)も兼務する。
金沢貴人氏(以下敬称略) DNPには、紙に印刷する事業がデジタル化の波に押されてどんどん減っていく中で、業態を大きく変えていかないといけないという強い思いが会社全体としてあります。
“ことづくり”で新規事業を創出するABセンターだけでなく、“ものづくり”の新規事業創出を担う部署も含めて活発に動いている中で、実際に新しい事業が立ち上がってくると、従来の印刷事業を主体として設計された会社の基幹システムでは対応できないケースもたびたび出てきます。
新しい事業に会社の仕組みを合わせようとすると、会社のインフラを担う情報システム部門においても、最新の技術を活用しながらフレキシブルに対応していく必要があります。
新規事業をつくる部門とIT部門である情報システム部門のバランスを取ることが重要で、そのバランス調整のために私が両方を見ているということになります。
――DNPは出版印刷を祖業としながら、さまざまな新事業の開発、多角化を図ってきました。1970年代から印刷工程のデジタル化に取り組んできましたが、そのことはDX、IT化の現代にどのように生きていると思いますか。
金沢 1970年代に汎用コンピューターを導入したのは画期的なことでした。当時はコンピューター自体が一般的ではない時代で、大企業の会計業務など用途も限られていました。
われわれは生産工程に汎用コンピューターを組み込んで、印刷用の原版(組版)をデジタルで作ろうと考えました。そうすることで原稿のデータの二次、三次活用がしやすくなり、将来的にいろいろな事業展開が見込めるという発想の下、取り組みを進めてきました。
かくいう私は、当時としては数少ないコンピューター系の学科を卒業した一人です。同級生の多くが汎用機メーカーを志望する一方で、私はコンピューターをうまく活用している企業に興味があり、その先端を行くのがDNPだと思い入社した経緯があります。
当社が早くからデジタル化に取り組んだことが、後のエンジニアの育成につながっていますし、ICカードの開発やCD-ROM版の電子辞書、電子書籍事業の創出へとつながっていったと考えられます。
DNPは2026年に創業して150年を迎えますが、当社の歴史の約半分の75年が経った時、「いつまでも出版印刷だけでは持ちこたえられない」という危機感がありました。これが今でも生き残るために「次は何をやるんだ」というチャレンジ精神、組織風土がDNAとして受け継がれているように思います。
「Lactobacillus paracasei KW3110(KW乳酸菌)」の開発と事業化が、日本農芸化学会2022年度「農芸化学技術賞」を受賞:時事ドットコム
[キリンホールディングス株式会社]
~キリンの免疫研究に高い評価~キリンホールディングス株式会社(社長 磯崎功典、以下キリン)のキリン中央研究所(所長 吉田有人)は、キリンが発見した乳酸菌である「Lactobacillus paracasei KW3110(以下、KW乳酸菌)」の開発と事業化が高く評価され、公益社団法人日本農芸化学会の2022年度「農芸化学技術賞」を受賞しました。なお、授賞式は3月15日(火)に日本農芸化学会2022年度大会(オンライン開催)にて行われます。「農芸化学技術賞」の受賞は、キリングループでは10回目となります。●受賞者キリンホールディングス株式会社 森田 悠治、鈴木 弘章、山崎 雄大、藤原 大介●受賞研究題目インフラマソーム制御を介した新しい眼の健康維持アプローチ:KW乳酸菌の開発と事業化●受賞研究内容【研究背景】高齢化やパソコン・スマートフォンなどの電子機器使用の増加などによって、私たちの生活スタイルは変化し、若年層の中にも目の老化や目の疲れ・不調を悩みとして抱える方が増加しています。その中で、食生活を中心とした日常生活における“目の健康維持”にも注目が集まるようになりました。また、加齢や外的刺激に伴う老化や機能低下に共通して存在する現象として「炎症」が注目されています。近年の研究で、この「炎症」を抑制することにより老化や炎症性疾患の緩和が期待できることが分かってきました。一方で、免疫の調節を介した目の炎症抑制効果を有する食品の研究報告は限られていました。【研究概要】・研究グループは、「KW乳酸菌」が免疫細胞の一種であるマクロファージ※1に作用して、抗炎症性サイトカイン(インターロイキン-10:IL-10)※2産生を誘導することを見出しました。そこで、「KW乳酸菌」による目に対する効果を2種類の非臨床試験において検証するとともに、目の疲れを感じている健常者を対象とした臨床試験において「KW乳酸菌」摂取の効果をフリッカー検査※3により評価しました。その結果、「KW乳酸菌」摂取4週目、8週目のフリッカー値の0週目からの変化量が、「KW乳酸菌」摂取群では対照群であるプラセボ摂取群(KW乳酸菌非摂取群)と比較して有意に高値を示しました。この結果は、「KW乳酸菌」摂取により、目の疲れを感じている健常者の目の疲労感が軽減される事を示唆していると考えられます。・「KW乳酸菌」が炎症を抑制する作用機序として、炎症や老化の進行への関与が報告されている分子であるインフラマソームの活性化を抑制する効果を、乳酸菌の中でも「KW乳酸菌」が特徴的に有することを発見しました。さらに、「KW乳酸菌」の乳酸菌表面の糖鎖※4の構造がIL-10産生を介したインフラマソーム活性化抑制効果に寄与している可能性も示しました。※1 免疫細胞の一種で、生体内に侵入した細菌などの異物を捕食して消化するとともに、さまざまなサイトカインを分泌し、傷の修復等を調節する役割を担う※2 炎症の重要な調節因子で免疫細胞などから分泌される低分子のタンパク質の総称※3 目の疲労度合を評価する指標の1つ※4 単糖と呼ばれる糖の分子が鎖状につながった一群の化合物●受賞者のコメントキリンホールディングス株式会社 R&D本部 キリン中央研究所 森田悠治免疫はヒトの健康にとって非常に重要な役割を果たしています。当社は、祖業であるビール事業で培った「発酵・バイオテクノロジー」を強みに、35年以上前から免疫の研究を重ね、「プラズマ乳酸菌」や「KW乳酸菌」の発見、作用機序の解明、そして商品開発に取り組んできました。今回の受賞は、これまで私たちが研究・商品開発に取り組んできた「KW乳酸菌」が、お客様に高い価値をもたらす素材であることを評価いただいた結果ではないかと、関係者一同、喜ばしく受け止めております。当社は、今後も免疫を中心とした研究開発を進めていくことで、お客様の健康課題を解決するとともに、ヘルスサイエンス領域を大きく成長させてまいります。●日本農芸化学会について農芸化学分野の基礎および応用研究の進歩を図り、それを通じて科学、技術、文化の発展に寄与することにより人類の福祉の向上に資することを目的として、1924年に設立された学術団体です。1957年に文部省の認可によって社団法人となり、2012年3月1日付けで公益社団法人へ移行しました。バイオサイエンス・バイオテクノロジーを中心とする多彩な領域の研究者、技術者、学生、団体等によって構成される本学会は、国際活動の推進、国際学術集会開催の積極的支援を実現し、実用性と応用性を基盤とする農芸化学の重要性を広く紹介しています。●農芸化学技術賞について農芸化学分野において、注目すべき技術的業績を挙げた正会員または賛助会員に授与されるものです。その業績は実用的価値があることが要件とされています。<日本農芸化学会 農芸化学技術賞ページ>https://www.jsbba.or.jp/about/awards/about_awards_tech.html キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。企業プレスリリース詳細へ
(2022/03/15-15:47)
J.フロント リテイリングのコーポレートベンチャーキャピタル、特別な感動体験に出会える予約サイトを展開するJapan Culture and Technologyに出資
[株式会社 大丸松坂屋百貨店]
大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つJ.フロント リテイリング株式会社(本社:東京都中央区、取締役兼代表執行役社長:好本達也、以下、当社)は、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田代友樹)と共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」(以下、本ファンド)を通じて、特別な感動体験に出会える予約サイトを展開するJapan Culture and Technology 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:飯倉竜、以下「J-CAT」)に出資します。今回の出資により、J-CATと共に、楽しみ方の多様化に対応し、特別な感動体験を提供する取り組みを進めてまいります。出資の背景当社グループでは、グループビジョンに“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”を掲げ、ステークホルダーの皆さまのWell-Being-Lifeの実現を目指しています。これまで大丸松坂屋百貨店では、松坂屋名古屋店の松坂屋旅行センターを中心として、「お客様を幸せにする旅」をコンセプトに、上質な旅をご提案してまいりました。くらしが移り変わる今、こころや生活を潤す「感動体験」に注目し、提案を強化するために、様々な希少性の高い体験コンテンツの開拓に取り組んでいます。J-CATでは、本物志向のハイクラスな会員様に向けて特別な感動体験に出会える予約サイト「Otonami」をはじめとするWebサービスを展開しています。「日本の魅力を感動体験として届ける」をコンセプトに、観光・レジャー領域における多彩なジャンルのプランを持つ、J-CATのサービス・コンテンツを高く評価し、今回の出資に至りました。今回の出資により、J-CATとともに上質で特別な感動体験ができる旅メニューの開発や、百貨店・パルコの店舗を活用した体験イベントを実施することで、こころ豊かなライフスタイルを提案してまいります。Japan Culture and Technology 飯倉竜 代表取締役 コメントこのたびの資本提携により、J.フロント リテイリング様と共に新たな取り組みができることを非常に嬉しく思います。大丸松坂屋百貨店やパルコのお客様に向けて新たな体験価値やお得な特典などをお届けし、心豊かなライフスタイルの実現に貢献したいと考えております。そして、当社の事業の軸である観光・レジャー領域における上質なコンテンツの開発を推進してまいります。Japan Culture and Technology(J-CAT)について国内向け体験予約サイト「Otonami(https://otonami.jp/)」と外国人旅行者向け体験予約サイト「Wabunka(https://otonami.jp/wabunka)」を中心に、日本の魅力を感動体験として届ける事業を展開。“文化”と“IT”をつなぎ、魅力あふれる日本の姿を世界へ広く発信していくことを使命としている。会社名 :Japan Culture and Technology株式会社所在地 :東京都中央区日本橋一丁目4番1号日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)5階代表者 :代表取締役CEO 飯倉竜設立日 :2019年11月URL :https://j-cat.co.jp/JFR MIRAI CREATORS Fundについてファンド名:JFR MIRAI CREATORS投資事業有限責任組合設立日:2022年 9月運用期間:10年運営規模:30億円運営者:イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社ファンドURL:https://cvc.j-front-retailing.com投資に関するお問い合わせ:[email protected]企業プレスリリース詳細へ
(2023/04/09-22:40)
生成AIをはじめとした新しいテクノロジーに情報サービス企業はどう向き合うのか『デジタル化による社会変化と新しいテクノロジーの活用 情報サービス産業白書2024』を6月28日(金)に発売 企業リリース | 日刊工業新聞 電子版
生成AIをはじめとした新しいテクノロジーに情報サービス企業はどう向き合うのか『デジタル化による社会変化と新しいテクノロジーの活用 情報サービス産業白書2024』を6月28日(金)に発売
...